LINE公式アカウント認証審査:落ちる理由と改善策
よくある審査落ちの理由
1. 審査基準を満たしていない:
LINE公式アカウントの認証審査では、「ユーザーに不利益を与えないか」「法令や規制に抵触していないか」「利用規約の禁止行為に該当しないか」「LINE社独自の基準を満たしているか」「LINE社の事業や信用を損なわないか」といった点が総合的にチェックされます (cf. LINE公式アカウントガイドライン)。
特に医療機関の場合、特に関連法規(医療法や薬機法等)の順守が重要で、法律違反となる表現やサービス内容があるとこの基準に抵触します 。
例えば、治療効果に関する誇大広告や薬機法で未承認の医療行為が記載されていると、法令違反のおそれがあると判断され審査に落ちる可能性があります。
2. LINEで開設できない業種・サービスに該当している:
LINE社はあらかじめ一部の業種やサービスを公式アカウント開設不可(NG業種)と定めています。代表的なNG業種の例として、医療(未承認医薬品の販売や個人輸入代行など)、出会い系、アダルト系、マルチ商法(MLM)やねずみ講、違法ギャンブル、個人情報の売買、偽ブランド品販売等が挙げられます。
医療分野でも、日本国内で未承認の医薬品を扱っていたり、薬の個人輸入代行を行っているようなクリニックは審査の対象外となります。
また美容系クリニックなどであっても、サービス内容や広告表現が医療法規的にグレーな場合はLINE側で慎重に判断されるため、「特定の医療関連サービス」は制限対象になり得る点に注意が必要です。
3. 他媒体(公式サイト等)の情報と相違がある:
申請内容と店舗の公式Webサイトや各種公的データに食い違いがあると審査落ちするケースがあります。
例えば、LINEアカウント上の名称や事業者情報が公式サイト上の正式名称と一致していない場合や、代表者ではない人物名義でLINEに登録している場合などです。
LINE側は申請時に提出された公式サイトや第三者機関のデータを参照してビジネスの実態や信頼性を確認するため、所在地・電話番号・クリニック名などの基本情報に齟齬がないかを事前に見直す必要があります 。
医療機関特有の注意点として、厚生局への届け出情報(クリニック名や住所)がWeb上の情報と異なる場合も不整合とみなされる可能性があります。
4. 申請フォームの入力不備:
申請フォーム自体に誤りや欠落があると、どんなに実態が適正でも審査に通りません。
よくあるミスとして、アカウント名を誤って個人名にしてしまう(公式にはクリニック名など正式名称を入れる必要があります)、LINE ID欄とアカウント名欄を混同して入力している、申込者氏名の欄に医院名やサービス名を入れてしまった、連絡先の電話番号・メールアドレスのタイプミス等が挙げられます。
特に医療機関では、院長個人名義でなくクリニックの公式名称で申請することが重要です。入力項目は細部まで正確に記入し、公式書類どおりの表記(法人格や「クリニック」「医院」等の表記揺れも含めて)に揃えましょう。
5. 業種カテゴリーの選択ミス:
LINE公式アカウント作成時に選択する業種カテゴリと、認証申請時に届け出た業種とが食い違っている場合も落とされる原因になります。
例えば最初に「美容サービス」としてアカウントを作成したのに、申請フォームでは業種を「医療機関」と記入したようなケースです。
この不一致はLINE側から見ると不自然なため、アカウント設定と申請内容の整合性を取る必要があります。
クリニックの場合、医療法上「医療機関(病院・診療所)」に該当するか、美容サロン扱いにすべきかなど業種区分が微妙なケースがありますが、LINE公式ガイドラインに沿った正しいカテゴリを選び直すことが大切です(不明な場合は事前にLINEに問い合わせることも検討しましょう )。
審査に通らない場合の対策・再申請時の改善策
1. ガイドラインと法令順守の再確認:
再申請する前に、LINE公式アカウントガイドラインおよび関連法規を見直し、自社のアカウント情報がそれらに抵触していないかチェックします。
特にクリニックでは、医療広告ガイドラインや薬機法に違反する表現がないかを確認しましょう。たとえば「最新の医療で必ず治ります!」のような断定的表現は避け、客観的事実に基づく表現に修正します。
また、LINE利用規約第18条の禁止行為(違法行為、公序良俗違反、第三者権利侵害など)に該当する恐れがないか再点検します。
2. ビジネス実態の信頼性向上:
審査担当者が安心して「公式である」と確認できるよう、公式サイトや第三者機関の情報を充実させましょう。
公式サイトは未完成ではなく内容を充実させ、クリニックの事業内容・診療科目・所在地・連絡先・院長名などを明確に掲載します。
医療機関の場合は、院内設備や医師の資格等も記載して信頼性を高めるのも有効です。必要に応じて各種医療機関データベース(日本医療機能評価機構や厚生労働省の医療機関情報提供制度など)に正確な情報が登録されているか確認し、LINE申請内容と矛盾がない状態に整えてください。
3. アカウント名・プロフィールの見直し:
アカウント名には必ず法人名や施設名など正式名称を含め、利用者にとって正式な機関だと分かるようにします。
個人名や愛称のみのアカウント名は避け、必要なら「〇〇クリニック公式」などと明示しましょう。
これは審査通過率を上げるだけでなく、利用者に対しても安心感を与える工夫です。またプロフィール写真や説明文も、公序良俗に反する要素や誤認を与える表現がないかチェックします。
プロフィールの説明には医院の簡潔な紹介とともに、必要に応じて所在地(○○市○○区など)や診療科を入れることで専門性が伝わりやすくなり、審査官にも目的が明確に伝わるとされています。
4. 正確な連絡先の提供と迅速な対応:
申請フォームに記入する電話番号・メールアドレスは、日常的に使用している直通のものを記載しましょう。
審査過程でLINE側から確認の連絡(電話やメール)が入る場合があり、これに応答できないと不利になります。実際に、審査期間中にLINE@チームからメールで質問が送られてきた事例も報告されています(メールアドレスの確認や追加情報の照会など)。
再申請時には審査中はこまめにメールチェックを行い、着信にも即対応できるよう準備しておくことが大切です。問い合わせが来た場合には丁寧かつ迅速に回答し、誠実に対応することで信頼度をアピールしましょう。
5. 書類・証跡の用意:
場合によっては、LINE側から事業実態を確認する資料の提出を求められることがあります。
クリニックであれば、開設届出書や診療科目の許可証など、公的な証跡を提示できるようにしておくと安心です。
再申請フォームに補足欄があれば、「○○クリニックは医療法に基づき開設届出済(届出番号○○)」などと記載し、正規の医療機関であることをアピールするのも有効でしょう。
公式サイトのURLも必ず記載し(フォームの該当欄がある場合)、誰が見ても正式なクリニックであると分かる状態にすることがポイントです。
6. 業種選択と内容表現の修正:
前項の「業種カテゴリーの不一致」があった場合は、アカウントの業種設定を修正し再申請します。
例えば美容クリニックの場合、「医療(美容外科)」など正しいカテゴリが用意されているか確認し、無ければ近しいカテゴリを選びます。さらに提供サービスの表現も見直しましょう。
場合によっては申請前にLINEの営業担当やサポートに相談し、「この内容で問題ないか」確認を取ることも検討してください。
以上の改善策を講じた上で再申請すれば、審査通過の可能性は高まります。
実際、一度不合格になっても修正を経て再チャレンジし、認証済みアカウントに承認されたクリニックは数多く存在します。
焦らずに問題点を洗い出し、着実に対応することで再申請での合格も十分可能です。
LINE公式ガイドライン・サポートに基づく重要ポイント
● 審査基準の透明性と対策:
LINE社は審査結果の詳細理由を開示しませんが、ガイドラインに審査の目的と確認ポイントが示されています。
前述した5つの審査基準 (LINE公式アカウントガイドライン)を念頭に置き、ユーザー視点・法令順守・規約順守という観点で問題がないか自己チェックしましょう。
また「当社独自の基準」は非公開ですが、一般常識的な社会モラルや信頼性が問われると考えられます。そのため、公序良俗に反する恐れのある要素や、社会的信用を損ねるリスクがないかも確認が必要です。ガイドライン上、「当社が不適当と判断した場合は利用不可」との包括的な規定もあるため 、少しでもグレーな要素は排除・改善しておくことが賢明です。
● アカウント名とプロフィール設定:
LINE公式ガイドラインでは、認証済みアカウント名に正式名称を含めることが必須とされています。
また一度認証されると基本的にアカウント名は変更不可であるため(名称変更には再審査が必要) 、最初の申請時に適切な名称を設定することが重要です。
クリニックの場合、「医療法人〇〇会 △△クリニック」のように法人名+院名を入れるか、長すぎる場合でも**院名(公式)**など公式性が伝わる名称にします。
またガイドライン上、アイコン画像もアカウント名に関連しユーザーに不自然でないものが推奨されています 。
ロゴマークや院の外観写真など、公序良俗に反せず公式性を補強できる画像を設定しましょう。これらは審査担当者への印象だけでなく、ユーザーに検索表示される際の信頼感にも直結します。
● 提出情報と公式サイトの一致:
ガイドラインには明記されていませんが、LINE for Businessのナレッジや各種事例から、公式サイト等の提出情報と申請内容が一致していることが重視されることが読み取れます。
そのため申請フォームに入力する会社情報・施設情報・連絡先などは、公式サイトやオンライン電話帳、Googleマップの掲載情報などと食い違いがないようにしてください。
特に医療機関では、名称の表記ゆれ(「クリニック」と「医院」など)や、住所表記の違い(ビル名の有無等)が起こりがちです。
些細な違いでも審査ではマイナスとなる可能性があるため、事前に公式サイトや各種登録情報を見直し、統一した情報を発信するようにしましょう。
● LINEサポートの活用:
LINE公式アカウントの管理画面やLINEヤフー for Businessサイトには、認証申請に関するFAQや問い合わせ窓口があります。
例えば「認証の再申請は可能ですか?」という質問に対して公式ヘルプでは「再申請は可能」と明言されています。
また再申請時には電話・メール対応も含め見直すよう促す記載もあります。
困った場合は遠慮せずにLINEビジネス担当者に相談するのがおすすめです。
医療系マーケティング会社やLINE運用代行企業の情報発信も参考になりますが、最終的にはLINE公式の判断が絶対ですので、公式サポート情報を優先的に参照しましょう。
● 認証バッジ取得後の留意点:
無事に認証済みアカウントを取得できた後も、ガイドライン遵守は継続的に求められます。
LINEは配信コンテンツに対する事前チェックこそ行いませんが、配信後にモニタリングを行っており、違反が見つかれば投稿削除やアカウント停止などの措置が取られ得ます。
特に医療機関の場合、後から追加したメッセージ内容やリッチメニュー内容が医療広告ガイドラインに抵触しないよう引き続き注意が必要です。
認証バッジは信頼の証ではありますが、それに慢心せず、利用規約・ガイドラインを定期的に見直しアップデートに対応することが、安全に公式アカウントを運用する秘訣です。
禁止されている表現やNG業種・カテゴリの具体例
最後に、LINE公式アカウントの審査や運用において避けるべき表現やNG業種の具体例を整理します。クリニックの担当者が特に気を付けるべきポイントを以下にまとめます。
NG業種・サービスの具体例
審査で認められない業種やサービスの例はガイドラインに列挙されています 。医療機関の場合直接当てはまるケースは限定的ですが、関連し得るものを含め代表的なNG項目を挙げます。
- 医療: 日本国内で未承認の医薬品、医薬品の個人輸入代行など(※正規の医療行為そのものは対象外だが、未承認治療や薬の違法販売はNG)
- 出会い系: 出会い喫茶、インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)等
- アダルト: 性風俗店(ソープランド、デリヘル等)やアダルトグッズ販売店、18禁コンテンツ配信など
- ネットワークビジネス: ねずみ講、マルチ商法(MLM)など連鎖販売取引
- 不安商法: 占いや霊感商法など人の不安や射幸心につけ込む商品販売
- ギャンブル: 賭博性の高いオンラインカジノ、違法賭博サービス
- 個人情報売買: 名簿業者など個人情報を不正に売買・仲介するサービス
- 偽ブランド品: 商標権を侵害するようなブランド品の模倣品販売
上記は一例であり、この他にもLINE社が不適当と判断した場合は認証後でもアカウント停止になり得ます 。
クリニック自体は適法に医療を提供する限りNG業種には該当しませんが、「健康食品のネットワークビジネスを兼業している」など複合的な事業を行っている場合は注意が必要です。そのような副次的事業がある場合、LINE公式アカウント上では触れない、もしくは事業自体を見直すことを検討しましょう。
禁止表現の具体例(医療広告におけるNG表現)
医療機関が発信する情報で特に問題となりやすいのが、医療広告ガイドラインに抵触する表現です。
これはLINEの審査のみならず法律上も禁止されているため、公式アカウントのプロフィールや投稿内容、そして公式サイト上からも排除すべき表現です。
代表的なNG表現例を以下にまとめます。
- 最上級・断定的な表現: 「最高の医療を提供」「日本一の実績」「必ず治る」「絶対に安全な手術です」等、効果や安全性を絶対的に謳う表現は禁止されています。
医学的に絶対安全・必ず治るという保証はできないため、誤認を与える恐れがあるためです。事実であっても「地域で最も症例数が多い」などの表現は慎重に検討し、可能なら第三者機関のデータ提示とセットにするなど工夫が必要です(それでも「日本一」「最高」は避けるべきです)。 - 比較優良広告: 「他院よりも優れている」「○○クリニックより安い」といった他の医療機関と比較して自院を優良と示す表現は認められません。競合他院を名指しした誹謗はもちろん、「地域で一番選ばれている」など間接的な比較もグレーゾーンです。LINE上でもこのような表現をプロフィールやトークで配信すると問題視される可能性があります。
- 患者の体験談・口コミ: 患者やスタッフの主観的な体験談を掲載することは禁じられています。例えば「○○治療を受けて奇跡的に治った!(患者談)」のようなケースや、アンケート結果を画像で貼り付ける行為もNGです。
医療広告ガイドラインでは、たとえ事実であっても個人の感想は他の患者に当てはまるとは限らず誤解を招くとして禁止されています。従って、LINE公式アカウント上でも患者の声をそのまま投稿することは避け、紹介する場合は一般論としてぼかすか、別途医療法上許可された範囲で行う必要があります。 - 有名人・権威の利用: 「モデルの○○さんも来院!」といった有名人の来院事実を過度に宣伝することや、「厚生労働省認可の専門医が施術」といった権威付け表現も注意が必要です。
前者は他院より優れている印象を与える比較広告とみなされる可能性があり、後者は専門医認定は学会の管轄で厚労省は関与していないため誤解を招く表現です。公式アカウントのプロフィールや投稿でも、このような記載は避けましょう。 - 術前術後の写真の扱い: ビフォーアフター写真を用いた宣伝も規制対象です。特に「加工・修正した症例写真」を用いて効果を強調することは虚偽広告に当たります。
LINE上で画像を配信する場合も同様で、必要以上に劇的な変化を見せる加工画像は避け、使用する際は各症例写真に施術内容・リスク・個人差等の詳細説明を添えることが求められます。説明無く写真だけを見せるのはNGと認識しておきましょう。
上記の禁止表現は一部抜粋ですが、医療機関の広告・宣伝に関する規制は年々厳格化しています。LINE公式アカウントの審査段階でもこれらがチェックされる可能性が高いので、申請前に公式サイトや配信予定のコンテンツから該当表現を排除しておくことが肝要です。
以上、LINE公式アカウントの認証審査におけるクリニック(医療機関)の留意点を、審査落ちの主な理由と対策、成功事例、ガイドライン上のポイント、そして禁止表現やNG業種の具体例という観点からまとめました。
特に2025年以降の最新動向も踏まえ、LINE社の公式ガイドラインや医療広告規制のルール 沿った形で解説しています。
認証済みアカウントの取得は手間もかかりますが、無事に審査を通過すれば公式検索での露出向上やユーザーからの信頼獲得につながります。本ページの内容を参考に、自院のLINE公式アカウント開設・運用を円滑に進めていただければ幸いです。

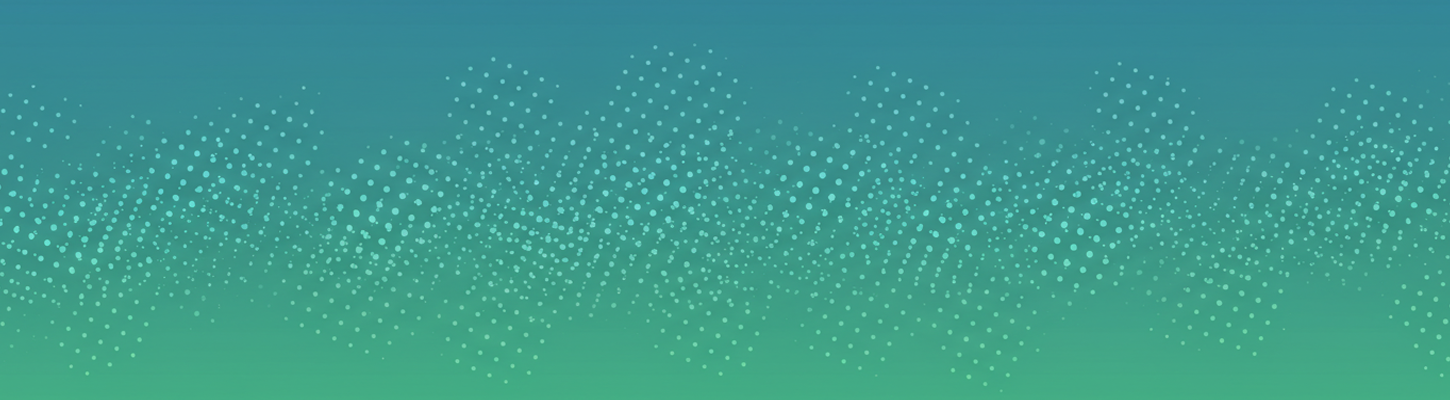
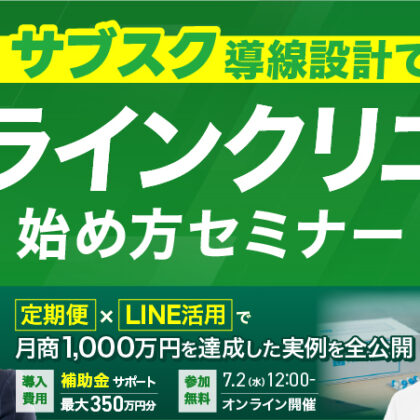




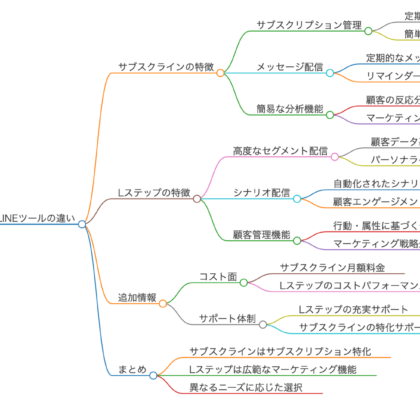
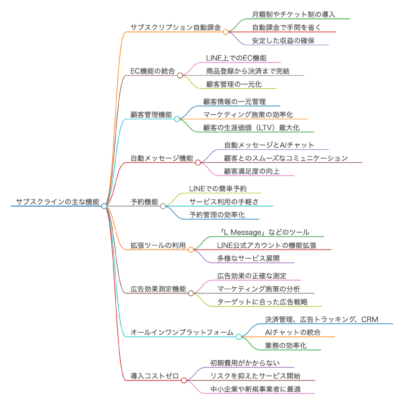
コメント